

近年、日本においてあらゆる方面における「国際化」が叫ばれて久しい。日本の国際的地位が高まり、その活動が世界の注目を浴びるようになったことは、日本人としては喜ぶべきことかもしれない。しかし、科学技術の発展といった面はともかく、島国であり、また単一民族という閉鎖的社会空間の中で育まれてきた日本人の気質に関しては、「国際化」を成し遂げる上で障害となる側面を未だ強く残していることも事実である。そして、それは教育における「国際化」を考える上においても、我々が考える以上に根深く存在している問題である。
今日、施設(設備)や法令の整備を担う、教育のハード面からの「教育の国際化」と、国際性ある人材を育成する人間教育のあり方を問う、教育のソフト面からの「国際化へ向けての教育」という両面から教育の「国際化」を考える必要性が問われるようになってきているが、本論文は、「国籍」という一つのキーワードを通して日本を眺めることによって、日本の学校教育における真の「国際化」を考える上での一つのアプローチとしようとするものである。

「国籍」というものが国際教育を考える上で重要なファクターになることは想像に難くないであろう。「国籍」の存在自体が、異なる国(文化)の存在を前提し、それぞれの国(文化)を尊重しつつ共存・発展を願う意味での「国際化」の必要性を暗に示唆しているからである。したがって、「国際化」を目指す教育にとっても、各国で「国籍」がどのような社会的位置や機能を持ち、かつどのような文化的位置や意味を持って扱われているかということを見つめ直してみる作業は、足元から「国際化」を考える絶好の題材の一つとなることができるだろう。
では、日本において「国籍」というものは、どのような社会的・文化的意味を持って存在しているのだろうか。
「国籍」の問題は、「国民」と「外国人」の境界をどのように定め、またどのような扱いの区別(差別)を設けるのかという問題でもある。従来、日本においては、日本国籍の取得は「父系属人(血統)主義」をとってきた。すなわち、父親が日本人の場合のみ、その子供は日本国籍を取ることができ、日本人と見なされたのである。(これに対し、アメリカのように、その国で生まれた者は全てその国の国籍を取れるとする方式は「属地(出生地)主義」と言われる。)
しかし、一九八四年の法改正(一九八五年一月一日より施行)により、「父母両系属人主義」を採用することとなった。両親のいずれかが日本人である(日本国籍を持つ)ならば、その子供も日本国籍を持つことが認められたのである。
とはいえ、この法改正は、日本の自主的な「国際化」の政策として行われたのではなく、国連における女子差別撤廃条約の調印問題に関する外圧の影響で、やむを得ず行った法改正であったという側面が強い。逆に言えば、日本人の一般的意識は未だ変わっていない、つまり「国籍」にまつわる何か日本独特ともいえるような意識が根深く存在しており、それが実質的な「国際化」を妨げる働きを持っていることを示唆しているともいえる。
「外国人」と「国民」の差
日本という国は、島国であり、また(基本的に)単一民族という環境により、異民族・異文化との接触がほとんどない歴史を持つため、明らかに異民族・異文化とのコミュニケーションが苦手である。と同時に、特に近現代史の反映であろうが、アジア系民族に対しては基本的に優越感のようなものを持っている(逆に言えばアジア系の人々をある種蔑視している)のに対し、西欧人(白人)に対しては劣等感や羨望感といった感情を持っている場合が多いように思える。アフリカ系など黒人に対してもまた独特の違った感情を持っているといえる。だから、厳密な意味では、「外国人」といってもその対象によって、感じる内容や接する態度など細かい点は異なっているといえる。そのことを踏まえた上で、以下では、日本における「国民」と「外国人」の間に、いかなる差(溝)があるのか、いくつかの例を挙げて考えてみたいと思う。
納税の義務は国民と同様
日本国憲法第二五条は、「国民」に対して、最低限度の文化的生活を営む権利を保証しているが、ここでいう「国民」は、「日本国籍保有者」を意味し、「外国人」は対象外とされる。また第三条では、「国民」に納税の義務を課しているが、ここでいう「国民」は、「国内滞在者」を意味し、「外国人」もその対象となる。したがって、二代・三代にわたって日本に定住している「在日朝鮮人」の人々は、納税の義務は「国民」と同様に負いながら、年金がもらえないなど、「外国人」として別格に扱われているという現実がある。
一方では、インドシナ難民の流入により、難民条約(日本は一九八二年に加入)との矛盾が指摘され、「外国人」も福祉手当が受けれるようになるなど改革が進められてきているが、これも外部からの影響によるものであり、日本人の意識の変革によるものではない。
「外国人」には戸籍はもちろん住民票もない。その代わりとなるのが「外国人登録法」に基づく「外国人登録証」である。これは常時携帯義務とともに、指紋押捺義務が課せられていた。指紋押捺に関しては法律制定当時から大きな問題とされてきたが、七〇〜八〇年代にかけて、「指紋押捺拒否」の問題が指紋制廃止運動とともに大きく取り上げられた。指紋を採取するのは、「同一人性の確認のため」とされているが、それは何も「外国人」にのみに必要なことではない。現に、それはあらゆる入試や選挙などの時に「国民」に対しても適用されるものである。そういった場合に限らず、「国民」にはそもそも指紋押捺の義務はない。よって「同一人性の確認」も、基本的に指紋によって行われることはない。
「外国人」にのみ指紋押捺を義務づけるその背後には、日本人の中に“「外国人」は何をしでかすかわからない連中だ。だから指紋とか取って厳しく管理しないと恐い”というような偏見的感情が根深く存在しているといえるだろう。(関東大震災時の朝鮮人虐殺事件はその典型ではないだろうか。)
現在では、指紋制廃止運動や、一九七九年の国際人権規約加入などに伴った改革により、「永住者は署名と家族事項の記入のみ。その他は一回だけの指紋押捺」というふうに変わってきている。指紋廃止運動は、日本人との連携による市民運動により大きな成果をもたらしたと言われており、その点で大きな意義を持つものだと思われる。
戦後保証の国籍による差別
最後に、「戦後補償」の内外格差に関する問題を挙げてみたい。日本政府は、被爆者、軍人、国家総動員法による徴用者、戦没者遺族などに対して、十五に及ぶ法律を制定し、国内向け戦後補償のためにこれまで累計40兆円近くを費やしてきた一方で、「被爆者二法」は例外として、そのいずれの場合にも「国籍制限」を設けて、旧植民地出身者などの「外国人」は適用対象外とされてきた。
これに対し、日本外務省の調べによると、サミット参加国のうち、日本とカナダを除いた(注‥カナダは植民地を持たなかった)米・英・仏・伊・西独の五カ国は、いずれも外国人元兵士に対して、自国民とほぼ同様の年金や一時金を支給しているという。
また、米国・カナダが第二次対戦中の日系人強制収容について謝罪と補償を行った際には、日本に帰国した人にも補償金が支給されている。アメリカの場合、ブッシュ大統領の謝罪文つきで一人当たり二万ドルというものであった。
一九九三年秋、国連の人権規約委員会において日本政府報告が審査された際に、席上の三人の委員から戦後補償における国籍差別が指摘され、人権規約の平等条項に合致するように是正することが勧告された。また、毎年八月十五日に行われる「全国戦没者追悼式」において追悼されている「三百余万」の人々は、日本側の死者のみを対象としている。そこにはアジアの犠牲者(二千万人ともいわれる)は眼中に入っていない。
このような戦後補償の内外格差の問題は、歴史認識の歪曲という問題とともに、今日にいたるまで大きな問題として残っているのである。
「地球市民」育成を目的に
以上のような問題の他にも、朝鮮人学校等に関連した「一条校」問題や、公務員採用に関する「国籍条項」の問題が最近でも話題となっているように、「国籍」という一つのキーワードだけをとってみても、そこから見えてくる問題は相当に深いものだと感じさせられる。
国際化時代の学校教育を考える際によく議論されることに「英語(外国語)教育」の問題がある。確かに、異文化理解・異文化コミュニケーションを促進する上で、異文化の言語理解はとても重要である。しかし同時に、異文化理解にはその文化の習慣や歴史そして現状を知ることが不可欠なのと同様に、まずは自分が属する国や文化がいかなる歴史・現状にあるのかということを知ることがいかに大切であるかを、この「国籍」をめぐる問題は私たちに教えているように思える。もちろん、自国や自文化の理解というものは、他の文化を知り、それと比較することによって初めて見えてくる側面が強いものでもある。ここで挙げた「国籍」の問題において、いろいろな改革が日本の自主的なものとしてではなく、外部からの指摘や圧力からなされてきた側面が強いことも、ある意味では致し方ないものだともいえる。
したがって、教育における「国際化」は、異文化理解や異文化コミュニケーションを促進する一方で、それを通して自文化を見つめ直し、より良い自文化、さらには「地球文化」を形成していくことができる、まさに「地球市民」を育成していくことを、その目的とするべきではないかと考える。これからますます異文化との接触機会が増えていくにしたがって、また一方で様々な問題が生じたり、隠されていた問題が明るみに出てくることも避けられないであろう。日本においては、歴史認識の問題はかなり大きな問題としてこれから取り組まざるを得なくなると思う。
まさに地球時代を迎えんとする二十一世紀を目前にしている今日において、教育における真の「国際化」は必須であるといえる。それだけに、特に学校教育においていかなる「国際教育」を為すのかという問題は、二十一世紀の人類の運命を担う最重要課題だといえるだろう。
<参考文献>
『在日外国人』(田中宏、岩波新書、1995)
『国際教育論〜共生時代における教育〜』(中西晃、創友社、1993)
『比較・国際教育学』(石附実、東信堂、1996)
その他:授業で配布された資料、在日朝鮮人に関する本・記事など
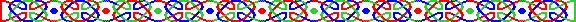
●平八・四・一四 元法制局長官 M・T氏
(一)解釈改憲に私が反対を表明したのは、一国の基本法の逸脱が国民の総意を離れてされてはならない、と考えるからなのです。国民の総意が賛成なら、個人的に反対であっても、一向構わないのです。一国の基本法を改めるには国民の総意の賛成を経なければならないことを政策立案者は篤と心し、それなりの努力をしなければならない、と思います。
(二)自衛隊は現憲法下法律で没することはできても、憲法に根拠をおかない法律で有事に際し即時適切有効な使命を達成することはできないだろうというのが、愚生の考えです。時代の変化とは無関係な、全く理論的な観点の問題です。
(三)集団的自衛権の憲法上の問題点は、自国が侵略されているわけでもないのに、いいかえれば自衛の絶対的必要性があるわけでもないのに、する武力の行使が自衛を逸脱し、現行憲法に定める「戦争の放棄」に直ちに違反しないと断じ得ないからです。いうまでもないことですが、国民の総意によって憲法が改正されるなら、話は別です。
●平八・四・一一 東京都文京区、元銀行頭取 M・I氏
歴史の事実と解釈、認識の問題はまことに難しいところでありますが、やはり時間の経過をまつ以外には客観的な評価はできぬのではないかと些か悲観的に考えております。
●東京都渋谷区、元警察庁幹部 J・K氏
「憲法改正案論考」を御恵送下され、誠に有難く、再三読み返して大いに勉強になりました。
●平八・四・二五 岡山市、養鶏業 Y・Y氏
「憲法改正案論考」を御恵贈賜わり、有難く厚く御礼申し上げます。
●平七・六・二二、同七・一九 川崎市−佐世保市、海上自衛隊幹部 N・M氏
御著述資料いただきました。部隊ではなかなか根源に係わるものに接して勉強する機会がありませんので、極めて有益に活用させていただきます。−−−私も艦隊のサチとして精励しております。いずれイージス鑑に戦隊旗を上げることを期しております。
●平七・四・八 東京都世田谷区、憲法研究家 S・M氏
此度は東大新報連載の資料をお送り下され、重ねて厚く御礼申し上げます。
国情益々騒然たる昨今、政界にあって数々の経験をふまれた貴殿の御健闘を大いに期待して居ります。「本立って道生ず」を昨今一層痛感して居ります。
以上掲載したものの他、多数の御意見等を聞かせて頂き、心から厚く御礼申し上げます。
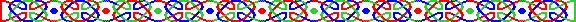
4.ストーンサークル(環状列石)
他のサルセン砂岩の彫刻は、地面近くに彫られている。その二つは紀元前一八〇〇〜一五〇〇年頃に、イギリスやアイルランドでよく使われていた斧の刃の部分であり、もう一つはギリシャ・ミケーネ文明の墳墓で見られる短剣に似た彫刻であるという。(日本テレビ 前掲書一一一頁)
大地を裂く斧は、雷電と共に男性を象徴する。剣もまた、蛇を象る男根のシンボルである。とすれば、楕円は女性を象徴するものとみてよかろう。
建造者ではない 初期ブリテン人
十七世紀に大英帝国の君主となったジェームズ一世は、ストーンヘンジを訪れて、お抱えの建築家イニーゴ・ジョーンズに建築物のもとの有様を図にし、説明を付すように命じた。ストーンヘンジ以外の記念物は、まだ気付かれずにいたらしい。ヒッチングによるとジョーンズはこう述べている。「ストーンヘンジが、初期ブリテン人によって築造されたものであるという可能性は、おそらくなかろう。彼らは野蛮で、獰猛で、着物を着るということを知らなかったし、堂々とした建造物を造るとか、ストーンヘンジのような驚くべき築造工事をなす能力は、全くなかったからである。」ジョーンズは、ローマ人がシーラスの神を祀ってストーンヘンジを建てたものと信じていた。
一六一一年に「大ブリテン史 ジュリアス・シーザーからジェームズ王まで」を著したジョン・スピードは、蛇紋様を体中に描きまくった裸姿の初期ブリテン人が、生首を掴んで仁王立ちしている絵をこの書に載せている。この絵をよく見て頂きたい。女性の全身は太陽、月、星、牛、鳥、植物などの図柄で埋め尽くされている。男性の体にはライオンが描かれ、腕には蛇らしいものが、足には連続三角模様やライオンや、蛇の鱗か鳥の足に見える図柄が表現されている。楯には◎と□・◇の重なった(★)幾何学模様などが見える。これがサタン崇拝者のシンボルでなくて何であろうか。
ドルイド僧の 蛇の寺院か?
ジョン・オーブレーは、ケルト民族のドルイド僧がストーンヘンジを造ったとする説を出しており、十八世紀にはウィリアム・スッタクリーもこの説を容認する本を出版している。スタックリーは、ストーンヘンジは蛇を信仰したドルイド僧が建てたドラコンティア、つまり、蛇の寺院であると主張した。
今日、ストーンヘンジはドルイド以前の構築物であることが明確になっている。それでもなお、ジュリアス・シーザーが伝えているドルイド教の様々な魔術、天文学と数学における発達、太陽崇拝、生けにえを捧げるのが慣例となっていた血の儀式や、荘厳な高貴さなどが、たとえ誤っているにせよ、この地に備わった解明し得ない荘厳さと神秘さに、無理なく調和している、とヒッチングはいう。
ケルト民族の祭 司階級ドルイド
ドルイド(Druid)は紀元前十世紀ごろライン川付近に発し、アイルランドまで及んだケルト民族の祭司階級である。一神教で霊魂の不滅を信じ、占卜により政治的、法的決定をなした。犠牲を司る祭司は細枝で大きな像を編み、人間をその脚部に入れて火をつけたという。人身供犠は豊穣のためになされた。
ドルイドは神殿を構えず、森の奥の天体のよく見える地を選んで、祭壇とした。聖なる森は堀や土手に囲まれ、中央には巨石群があったともいわれる。オークを神聖視し、これに宿るヤドリギを聖なるものと見なしていた。
シーザーの「ガリヤ戦記」(第六巻)やプリニウスの「博物誌」(第一六巻 九五)などが、今は消滅してしまったドルイドについての記録を残している。
神聖視されたオ ークのヤドリギ
ドルイド(drus<木、特にオーク>+wid<知)とは、「オーク(カシ、ナラ)の知恵をもつ者)という意味らしい。ヨーロッパは新石器時代の人々が居住した頃から、深いオークの森に覆われていた。オークは落葉樹であるから、秋・冬には葉を落とす。この中で、そのヤドリギだけは青々と葉をつける。それで古代人はオークの木の生命がヤドリギに宿ったと考えたのではなかろうかという。
タキトゥス(五五〜一一七頃)の「ゲルマニア」第三九には、ゲルマニアの古い樹木信仰に関する報告があり、一定の日に北ドイツのエルベ河周辺に居住したスエービー族が全員聖なる森に集まって、人身御供の儀式をしたという。アルプス以北の北西ヨーロッパの森で、こうした犠牲の儀式を執り行なったのがドルイド僧であった。(安田喜憲 「大地母神の時代 ヨーロッパからの発想」角川書店 一九九一 一六八、一七六〜七七、一五三頁)
プリニウスの「博物誌」によると、白い衣を着たドルイド僧は、オークの木に登り、金色の鎌でヤドリギを切り落とす。僧はそれを白衣の中に受け止め、オークの木の下で犠牲の儀式を行なう。ヤドリギは最大の生殖力と解毒剤であるという。
「金枝篇(The Golden Bough)」を書いたフレイザーによると、伝説にいう金の枝とは、このヤドリギのことであろうという。この枝を切って数ヶ月おくと、黄金色に変わるのだという。現在ストーンヘンジで夏至の儀式を行なっているのは、同名の教団を名乗る秘密結社である。
(つづく)
|ホームへ戻る|
 t-shinpo@super.win.or.jp
t-shinpo@super.win.or.jp