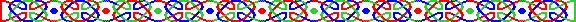
花だより(362)
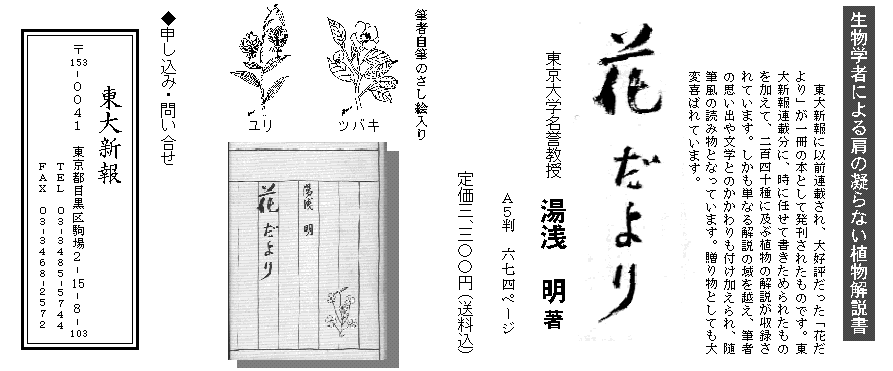
東京大学名誉教授 湯浅 明
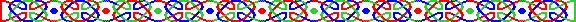
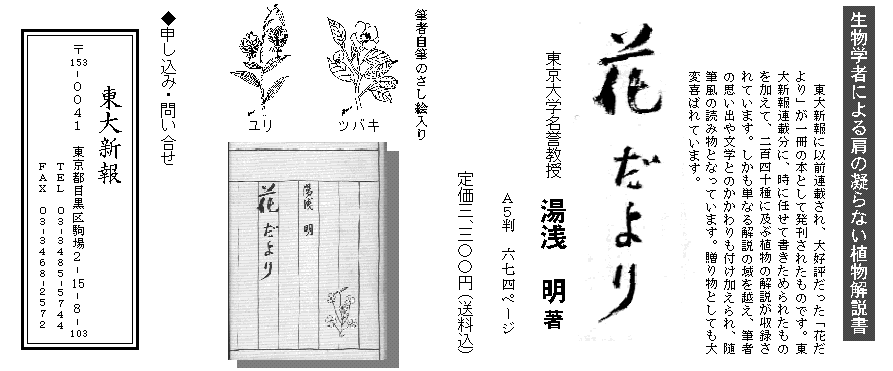
東京大学名誉教授 湯浅 明
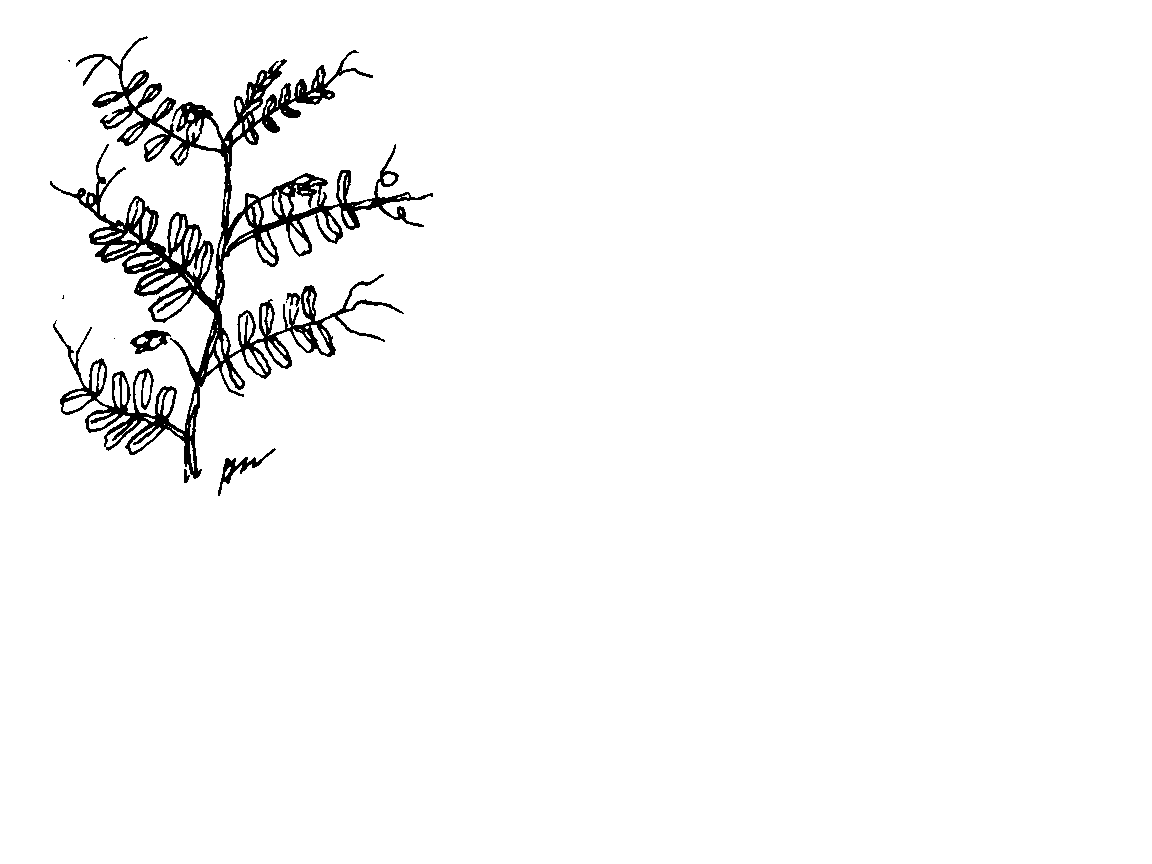 スズメノエンドウは山野の日当りに生えるマメ科の一年生草本。高さ50㎝くらいで、茎は4稜で細く弱々しい。葉は互生して偶数羽状複葉で、その先は分岐した巻ひげとなっている。四~五月頃、葉掖から花柄を出し、白紫色の蝶形花を3~4個つける。がくはつりがね形で5裂し、花後、果実はさやとなり2個の種子をふくむ。全草を牧草とし、また茶として飲む。
スズメノエンドウは山野の日当りに生えるマメ科の一年生草本。高さ50㎝くらいで、茎は4稜で細く弱々しい。葉は互生して偶数羽状複葉で、その先は分岐した巻ひげとなっている。四~五月頃、葉掖から花柄を出し、白紫色の蝶形花を3~4個つける。がくはつりがね形で5裂し、花後、果実はさやとなり2個の種子をふくむ。全草を牧草とし、また茶として飲む。スズメノエンドウは雀野豌豆で、雀は小さい意味で、小さなノエンドウという意味である。学名はVicia hirsuta Kochといい、Viciaはこの植物のラテン古名で、この属の植物につる性のものが多いのでラテン語のvincire(巻きつく)を語源としている。hirsutaは「粗毛の」で、がくや果実に毛があることによる。
スズメノエンドウと同属(Vicia)のカラスノエンドウは日当りに生える越年生草本で、茎は四角柱状で、葉は偶数羽状複葉で互生し、小葉は倒卵形または線形で、ほとんど柄がない。四~五月頃、葉掖に紅紫色をおびた蝶形花を1~2個つける。がくは鐘形で先端5裂し、濃紅紫色である。果実はさやで長く、熟すると黒くなる。10個くらいの種子を含む。牧草となり、種子は食べられる。
和名カラスノエンドウは、スズメノエンドウに比べて全体が大形で、果実が黒いことにより、また、小葉の先が凹んで矢筈に似ていることからヤハズエンドウともいう。カラスノエンドウの学名は、Vicia sativa L.といい、sativaは「栽培された」である。カラスノエンドウの染色体数は2n=12である。
スズメノエンドウと同属(Vicia)の日本産植物には、カスマグサ、カラスノエンドウ(ヤハズエンドウ)、ツルナシカラスノエンドウ(ツルナシヤハズエンドウ)、ホソバノカラスノエンドウ、イブキノエンドウ、クサフジ、オオバクサフジ(ハマクサフジ)、ツルフジバカマ、ナンテンハギ(タニワタシ、フタバハギ)、ミヤマタニワタシ、エビラフジ、ツガルフジ、ヨツバハギ、ソラマメなどがある。
スズメノエンドウと同属のソラマメは、西南アジア、北アフリカの原産で、日本では各地に栽培される。茎は4稜で、高さ60㎝くらい。1~3対の偶数羽状複葉で互生し、小葉はだ円形または卵形。春に葉掖に白色または淡紫色をおびた蝶形花を横むきにつける。果実はさやで、大きく、ふくらみ、数個の種子(豆)をふくみ、食用とする。
生のソラマメには一般に炭水化物(主にでんぷん)、10~15%、粗たん白質7~12%、粗脂肪約5%、灰分約1%を含む。灰分中にはりん、カルシューム、鉄、銅、ナトリウム、ほう酸などが検出されている。ビタミンBも比較的多い。
ソラマメは蠶豆と書き、学名はVicia Faba L. forma anacarpa Makinoといい、Fabaはラテン語の「豆」、anacarpaはラテン語のana(上方に向った)+carpos(果実)で、果実のさやが上に向うことによる。
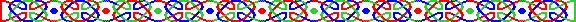
五、九州王朝
紀元前一〇〇年頃の天孫降臨に始まり、一世紀の後漢光武帝から「漢委奴国王」という金印を授与された委奴国、三世紀の魏朝から「親魏倭王」という称号を授与された卑弥呼・壱与の邪馬壱国、五世紀の倭の五王の邪馬臺国、七世紀の「日出づる処の天子」を自称して遣隋使を送った多利思北孤のたい国と継承され、白村江の戦いで滅亡させられたのが九州王朝である。
その歴史は、今後つぶさに追っていくが、中国を中心とする東アジアの政治動向、朝鮮半島をめぐる覇権闘争にかくも敏感であったかと思われるほど、当時の国際的秩序の中で、外交と軍事を駆使して諸国と渡り合っていたことが分かるのである。
天孫降臨の真実
天孫降臨は弥生時代前期のことであるとされ、それまで八百万神の長であった出雲王朝の大国主神に対して第一の臣下であった天照大神が、金属器(青銅)・矛の威力を借りて権力委譲を迫り(国ゆずり)、その上で本貫の対馬(阿麻弖留神社が存在する)・壱岐(対馬は宗教的中心、壱岐は生活的軍事的中心)を中心とする海峡国家=天国=海人国から豊饒な縄文時代以来の農作地帯(唐津菜畑遺跡から博多板付遺跡まで縄文水田の跡が確認されている。この北部九州の農業技術が東北津軽に伝わったことは有名であるが、それを伝えたとされる安日彦・長髄彦は原九州王朝=豊葦原の千五百秋の瑞穂の国のリーダーであったとも考えられる。津軽の神々である荒吐覇も、もともと原九州王朝の神であったと考えられ、博多湾岸には「荒」の地が多く見受けられる)へと、天照大神の孫ニニギノ命が天孫降臨を果したのである。ニニギノ命は筑紫の日向の高千穂のクシフル峯=高祖山連峰に降り立ち、宮殿を造り、筑紫の日向の可愛の山陵に葬られた(これは吉武高木遺跡である可能性が高いと指摘されている)とされている。
ニニギノ命と 漢文的教養
ニニギノ命は天孫降臨の地において、「此地は韓国に向ひ、笠沙の御前を真来通りて、朝日の直刺す国、夕日の日照る国なり。故、此地は甚吉き地」と述べたと『古事記』に書かれており、この記述は、
「向韓国真来通
笠沙之御前而
朝日之直刺国
夕日之日照国」
という漢字六字ずつの四行の対句形になっていることが分かる。これは日本式対句漢文と言ってよく、
「此の地(糸島郡、高祖山付近から望む)は、
(北なる)韓国に向かって大道が通り抜け、
(南なる)笠沙の地(御笠川流域)の前面に当たっている。そして、
(東から)朝日の直に照りつける国、
(西から)夕日の照る国だ。」
という「四至の文」になっていることが注目される。これは中国の伝統的用法に立った、臨地性の強い的確な表現なのである。
今日に伝わる 「大祓(おほはらえ)の祝詞」
さて、ニニギノ命に関係が深く、今日まで伝えられているものとして、祝詞と君が代が挙げられる。
例えば、二十世紀の現代でも祭儀の時に実際に用いられている祝詞の中に「大嘗祭の祝詞」「大祓の祝詞」がある。後者は「六月の晦の大祓(十二月はこれに准へ)」とも呼ばれ(六月と十二月の年二回行われるようになっていた点、同じ弥生時代後半の倭国で、『三国志』魏志倭人伝に出てくるように、二倍年暦が用いられていたことが思い出される)、ニニギノ命の天孫降臨の際に生じた「天皇が朝延」の様々な罪を祓う内容となっている。
君が代誕生の秘話
また、国歌君が代もその起源を知る人は少ないが、その歌詞に出てくる地名は北部九州に集中している。
例えば、狭い糸島平野にほぼ二列になって道路沿いに十社ほど、天降神社という不思議な名前の神社が存在しているが、その糸島郡の西端に桜谷神社があり、その祭神は苔牟須売神・木花咲耶姫神となっている。そして、同じ糸島郡の三雲遺跡・井原遺跡などがある倭国の「王家の谷」とも言うべき地に細石神社(祭神=磐長姫・木花開耶姫)がある。ところで、井原というのは岩羅のことであり、北部九州には早良(=沢羅)・磯羅といった「~羅」型地名が多くあり、対岸の朝鮮半島でも新羅(ギ=城・柵の意)・百済といった地名が見られる。イワラというからには「岩」の地であったということであり、縄文時代に巨石信仰があったことを思わせるのであるが、弥生期金属器を持った天国軍が縄文期巨石文明・稲作文明の中心に天孫降臨を敢行したということが分かるのである。
さらに博多湾東部が千代の松原と呼ばれていることをふまえると、狭い糸島郡・博多湾岸に三十一文字の君が代の歌詞の中の四つの固有名詞が含まれていることになるのである(君が代は 千代に八千代に さざれいしの いわをとなりて こけのむすまで)。
ちなみに金印で有名な志賀島の志賀海神社では、その祭りの中で風俗歌・地歌として君が代が歌われているのである。つまり、君が代は本来九州王朝の内部で作られ、歌われ、奉納されていた歌だったのである。
この志賀海神社の祭りでは、第一部で先述の「大祓の祝詞」がまず唱えられ、第二部で八乙女の舞(後の倭国に卑弥呼・壱与が擁立されたように、霊的能力を持った女性リーダー・巫女女王といった存在を髣髴させる)がなされる。そして、第三部の闇のお祭りを経て、第四部の山ほめ祭りで君が代が述べられるのである。
しかし、この君が代の「君」とは実は女性を指していることに注意しなくてはならない。『隋書』たい国伝によれば「阿輩鶏弥=我が君、鶏弥=君(王の妻)」となっており、桜谷神社の祭神苔産霊神は石長姫命のことだとされている。ニニギノ命が天孫降臨した時、その筑紫には大山津見神がおり、彼には石長比売(磐長比売、姉)と木花之佐久夜毘売(妹)の二人の娘がいた。ところが姉は大変醜く、妹は無類の美人であり、大山津見神はニニギノ命に姉と結婚してくれるように求めたが(そうすることで岩のように長寿になるという)、彼は姉を追い返し、妹と結婚した。かくして、天皇の命は花のように短くなったと記紀には書かれている。
ちなみに神話で落としめられている神々とは、前時代までの「輝ける神」であることが多い。ヒルコ(今でも西日本各地では輝ける神として尊崇されており、恵比寿も実はヒルコ大神である)しかり、スサノオしかりである。わざわざイメージを壊す必要があるほど、前時代前王朝の「輝ける主神」であったことを逆に証明していると言えよう。磐長比売が「甚だ凶醜(まがまがしく醜いこと)」「見畏れて返し送りき」と酷評されているのは、裏を返せば弥生時代の前、縄文・旧石器の文明世界(巨石信仰・岩石崇拝の時代である)では、「輝ける中心の女神」として尊崇されていたということである。
こうした「磐長比売信仰」を背景にして作られた賛歌が「細石のいわおとなりて苔むすまでに」である。「君が代は千代に八千代に」の「君」とは本来「女神」を指すものであり、「磐長比売の神徳が末の末の世まで永遠に続くことを願う」と歌った「神歌」だったのである。
君が代は九州王朝の賛歌であり、博多湾岸の王者・筑紫の君への賛歌として唱えられていたものであったが故に、古今集の編者紀貫之(彼は近畿天皇家側の人物である)は巻七・賀の部の冒頭で、「題知らず」「読み人知らず」としてこの歌を載せたのであろう。「大和朝廷ではない他の先在王朝の歌」であることを知っていたからこそ(平家物語でも朝敵となった者の実名を勅撰和歌集に載せることはできないので、「読み人知らず」として掲載するという平薩摩守忠度をめぐる逸話が巻第七に載っている)、このような作為がなされたと見ることができるのである。
(つづく)
|ホームへ戻る|
 t-shinpo@super.win.or.jp
t-shinpo@super.win.or.jp