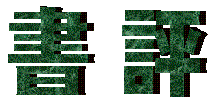
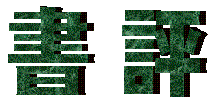
夏休みの読書案内
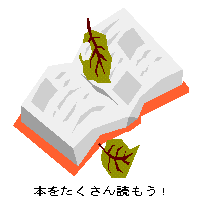
最近の歴史教科書論争に、そもそも歴史教育とは何かという視点から一石を投じたもの。著者によると、歴史教育とは、日本人としての共通意識、つまり「国民の物語」を教えるもので、それゆえ基本はあくまでもオーソドクスでなければならないという。そもそも「ヒストリー」には、「歴史」と「物語」の二つの意味がある。それを日本の場合、歴史だけに、さらに学校教育では歴史年表だけに矯小化したきらいがある。だから多くの学生が歴史は暗記ものだと思っている。本当は、過去、現在、未来を生きる「私」を形成する上で、欠くことのできない来歴であるのに。
戦前の国粋主義的な歴史教育に対する批判から、戦後は客観的、科学的に歴史を教えることが正しいと思われてきたが、それとて唯物史観という別の大きな物語として歴史を捉えようとする思想の影響によるものであった。戦後50年を越えた我々は、そろそろ外からの物差しによらない、日本人としての物語を創り上げるべき時を迎えている。
例えば日本史の核心である天皇について、明治の元老たちは日本人が抱いている天皇へのイメージを正しく把握して、五箇条の御誓文で「万機公論に決すべし」と、天皇の権威による民主政治を行おうとした。それは戦後の天皇の人間宣言、新憲法における象徴天皇にも通じるもので、その意味で憲法としての連続性がある。占領軍といえども、それを無視してまで都合のいい憲法を押し付けることはできなかったのである。
愛国心は、親への愛と似ているというのも分かりやすい。どの親のもとに生まれるかは、子供が選ぶことはできない。また、良い親だから愛するという比較の問題でもない。まさに親だからこそ、良い点も悪い点もひっくるめて愛する。言い換えれば我が身に引き受けるという姿勢である。そういう愛国心を教えられないのが、今の歴史教育の最大の欠陥であろう。 (T) (PHP新書、本体657円)
キリスト教は、イエス・キリストという歴史的人物を中心に形成された世界宗教である。しかし、イエスの生涯の記録は乏しく、処女降誕をはじめ数多くの謎に包まれている。ただし、イエスが実在したことは確かであろう。
ところが、イエスの人生の中で、完全に失われた十数年間がある。聖書には、12歳の出来事、すなわち、「過越の祭り」の時のことが記されているが、その後、30歳で公生涯を出発するまでの期間は何の記録もない。本書は、そのミッシングリンクに一つの解答を与えるものとも言える。
「聖イッサ説」によれば、イッサ(イエス)は13歳の時、神の言葉における完成を目指し、東方に向けて出発した。そして、インドやヒマラヤのふもとでブッダの法を学びながら、神の教えを説いていたという。その伝説はフィクションにすぎないと批判されてもいるが、イッサの言葉は実に真理性に富んでいると評価できる。いわゆる凡人では、その言葉を発することができないと思われる。
例えば、「父なる神はわが子に、どんな差別も置いてはいない。父なる神にとっては万人が平等であり、万人ひとしくわが父の愛するものです」。「至上の幸福は、清く身を保つことによって得られます。それだけでなく、他人を導き、未来の完成を得させることによっても同じことです」等々。
キリスト教と仏教とでは大きな相違があると思われているが、もし聖イッサ伝が真実であるとすれば、その間の距離は一気に短縮されることになろう。真の世界平和が願われる今日においては、その真偽性はさておくとしても、さまざまな意味で非常に興味深い内容だと言える。
(Y)
(立風書房 1900円)
イギリス人のアーネスト・サトウは徳川慶喜について、将軍は自分がかつて見た日本人のなかで、もっとも貴族的風采の一人である。秀麗な顔立ちをもち、額は高く、鼻筋はよく通り、じつに好紳士であった」と回想録に書き残している。当時、イギリスは薩摩藩につき、フランスが幕府を応援していたのだが、サトウはよほど慶喜に好意をもっていたのであろう。もちろん、それは風采だけではなく、その見識と手腕に対してである。
明治維新は革命と呼んでいい動乱であるから、もっと多くの血が流されてもおかしくはなかった。その悲劇を防いだ最大の功労者が慶喜である。彼は将軍でありながら、300年続いた政権を自らの手で大政奉還した。その奇想天外のアイデアは、坂本龍馬が考えたものだが、慶喜が将軍職に就いていなければ、実現は難しかったであろう。老中や大名、倒幕の志士たちよりも、よほど世界の情勢に通じていた。その時勢の流れのなかで、彼はアクロバットを演じるだけの才覚を持ち合わせていた。
しかし、根っからの革命家である西郷は、流血を要求した。それが鳥羽・伏見から始まる戊辰戦争の原因である。それに対して慶喜は、さっさと軍艦で大阪から江戸に帰り、さらに水戸に引きこもって、ひたすら隠忍自重する。当然、幕府側の人たちからは裏切り者と非難された。
その姿勢は明治になってからも変わらない。旧幕臣や政治的臭いのする人物には一切面会せず、ひたすら趣味の世界に生きた。反政府のシンボルに祭り上げられるのを極端に恐れたからである。国民の大半にとって明治はひどい時代であった。農民は年貢が上がり、武士は職を失い、西南の役のような内乱もあった。そんな日本が、列強の植民地とならなかったのは一つの奇跡といっていい。慶喜に対する評価が改まってきたのは、明治30年以降のこと。倒幕・維新を歴史として語れるようになってからである。 (T)
(文藝春秋、本体1238円)
97年11月2日、NHKスペシャルで放映されたドキュメントの活字版である。舞台は北アイルランド。カトリックでありながら、警察のスパイとなってIRA(北アイルランド共和軍)に潜入した若者と、その家族を描いている。彼はテロ情報を流すことで多くの人命を救ったが、発覚してリンチの危機に。しかし、隙を見て逃走、現在はイギリス本土で逃亡生活を続けている。警察に「密告」し続けた彼は、今はIRAに「密告」されることに怯える日々。強く愛し合いながらも、母と子が一緒に暮らすことはできない。
母はIRAのテロには反対だが、プロテスタントに対する憎しみは強く、アイルランドヘの統合を支持している。息子も他の子供たちと同じように、プロテスタント系住民や警察へ投石するのを当たり前のようにして育ってきた。そんな彼がどうして警察のスパイになったのか。原因の一つはIRAが武力派と穏健派に分裂したことで、彼の尊敬する義兄が武力派のテロにあったこと。もう一つは、当然ながら警察サイドからの工作である。個人的信頼関係と金銭の授受の積み重ねで、スパイは成立する。007の国であることを忘れてはならない。
北アイルランド紛争は日本人の理解を超えている。先進国のイギリスで、宗教の違いを理由に、どうして30年も殺し合いを続けているのか。そうした疑問に答えるため、簡潔に紛争の歴史的背景と、現実の人々の暮らしを書き込んでいるのが理解を助ける。もともとは12世紀、ローマ法王のお墨付きで、イギリス国王がアイルランドに侵攻したのがことの始まり。その後も力による支配と抵抗の歴史が続いてきた。それはまさに憎しみの連鎖である。
NHKの「家族の肖像」は冷戦後の世界で、悲劇の中に生きる家族の姿を描いていた。平和と豊かさの中で崩壊する家族の危機とは別の風景が、今の時代にもはるかに多いことを痛感させられる。 (T)
(NHK出版、本体1700円)
「死線」には肉体的な生命の危機という意味もあるが、もっと感心するのは、彼の政治生命の強靭さである。1992年の大統領選挙で金泳三に破れたあと、政界からの引退宣言をしたのに、93年にはそれを覆して新たな野党を結成した。興味深いことに、韓国の人たちはその変心をあまり非難しない。絶望するも情、変心するも情、そうした情の深さとして彼を理解し、好んでいるからであろう。現在、世界の政治家の中でもとりわけ情熱と志を感じさせる人物の自伝である。
大統領選挙の折、足許がおぼつかないように見えたのは、1971年の暗殺未遂事件でトラックが、乗っていた車に突っ込み、股関節に障害を負ったからだ。73年に東京のホテル・グランドパレスから拉致された、いわゆる「金大中事件」では、ロープで縛られて船の甲板に転がされ、海に投げ込まれそうになった時、目の前に突然イエスが現れたという。そして、「まだやり残したことがあるので助けて下さい」と祈った途端、赤い光が走って、「飛行機だ!」という声と共に男たちが逃げて行った。その後、近付いてきた人に助けられたのである。事件は政治決着したため真相は闇の中だが、本人ならではのエピソードが書かれている。彼は張勉元首相の影響でカトリック信徒になっていた。
仇敵、朴正煕大統領が暗殺されてからも状況は変わらず、80年には金斗煥政権下の裁判で内乱陰謀罪等により死刑判決を受ける。光州事件の学生を扇動したというのである。その後減刑され、病気治療の名目で米国に渡る。実質的には亡命であった。完全に権利を回復するのは、盧泰愚政権になってからである。
歴代すべての大統領が、予期せぬ死か失望の内に政権を去って行った後、最後の貧乏くじを引いたといわれる金大中が、瀕死の韓国でどんな手腕を振るうのだろう。死から何度も蘇ったその人生に期待したくなる。 (T)
(千早書房、本体1800円)