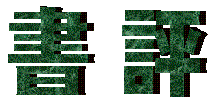
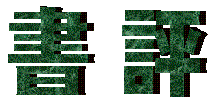
今の社会において、学校の価値はかなり相対的になっている。経済が発展し、社会が多様化した結果であるので、親にとっても子供にとっても、それは同じこと。ところが、親には自分が学校に通っていた頃の、学校へ行くのは当たり前というイメージが強く残っているため、子供が学校に行かないのを許せない。そんな大人の価値観に縛られると、子供も学校に行けないことに苦しむようになる。そうした不幸のループから抜け出すための代表的な試みを取材したのが本書である。
「東京シューレ」は、登校拒否児たちのたまり場として、85年に元小学校教師の奥地圭子さんが設立したもの。長男が小3で、次いで長女が小6で登校拒否になり、その対応から自らの学校信仰の強さに気づいたのがきっかけで、親の学びあい、支えあいの必要を感じたからだ。親が「学校に行かなくてもいいよ」と言えるようになると、子供たちも自立の糸口をつかむようになった。
「賢治の学校」を始めた鳥山敏子さんも、30年間、小学校教師を務めた人。子供のありのままの存在を受け入れたいという親たちを集め、ロールプレイのような「ワーク」を通して、子供の気持ちや親の深層心理に気づかせ、それぞれが自分自身を変える手助けをしている。
最も多くの頁を割いているのが、シュタイナー教育の紹介。人間の霊的側面を重視し、「人智学」を唱えたドイツの思想家で、20世紀初頭に新しい教育運動を起こし、今では世界各地に650のシュタイナー学校が広がるなど、成功を収めている。創造的想像力が伸びる幼児期には童話や昔話を聞かせ、感受性が伸びる児童期には、芸術に触れる機会を多くし、学ぶ楽しさを養うのが基本。それがあれば、14歳頃には、自然と将来への希望を持つようになるという。
いずれのケースもキーワードは「自立」で、子供の自立を願う前に、まず親自身の自立が問題だということに気づかされる。
(T)
(共同通信社、本体1600円)
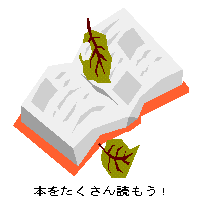
挑発的なタイトルのいう「理由」を要約すると、第1に政治の論理が経済の論理を優先していること。韓宝鉄鋼工業の倒産で明らかになったように、体力を越えた借金、評価の定まっていない工法の導入など、あらゆるビジネスに賄賂が絡んで、合理的な判断がなされていなかった。しかも、それを主導したのが大統領の息子なのだから、本来なら責任を取って大統領が辞職して当然の事件である。手抜き工事で、デパートや橋の崩壊が問題になったが、近代社会にはそぐわない不条理が、いまだ横行しているのである。
その第二は、国民が自分の利益を考えるだけで、他人を思いやらないこと。ソウルオリンピック当時、街はごみ一つなくきれいだったが、それが終わると誰もゴミを拾おうとしなくなったという。著者は、住んでいる町の自治会で町内の掃除を呼び掛けたが、賛成されなかった。自動車が接触事故を起こすと、路上でいつまでも言い争いをして、そのために渋滞が起こっても知らん顔。信号が変わるとわれ先に飛び出すので、ソウルは世界でも最も交通事故の多い都市の一つになっている。
著者は商社マンとして、30年間韓国でビジネスをし、特に浦項製鉄所の建設では、外国人としてただ一人大統領から表彰されている。本書は、その30年間の体験を本音で語ったもので、ごくごく当たり前のことばかり。浦項製鉄所の成功は、朴泰俊会長が半分のエネルギーを割いて、政治的圧力を排除したからだという。軍出身で、朴正煕大統領と太いパイプのあった朴会長でさえそうなのだから、後はおして知るべしだろう。
しかし、日本人によるこの本が、この題で韓国で出版され、30万部のベストセラーになり、著者は特に迫害されるわけでもなく、講演に引っ張りだこの人気という事実に、むしろ韓国の成熟を感じる。しかも、原書の出版社は、学生運動のために就職できなかった若者たちが創業したという。題とは別に韓国の新しい力を予感させる本である。
(T)
(文藝春秋、本体1524円)
ドイツはごみの徹底した分別収集やリサイクル、メーカーの廃棄物回収責任、さらにはダイオキシンを発生するごみ焼却の禁止など、環境保護が進んだ国として知られている。寒冷な風土のため、一度緑が破壊されると、その回復には莫大な労力を要する。かつて酸性雨のため、ドイツのシンボルとも言えるシュヴァルツヴァルト(黒い森)が枯れかかったことが、環境運動の盛り上がりを呼んだ。ドイツの環境は、政府の政策によって守られているのではなく、一人ひとりの市民の努力によって守られていることが、その代表的な10人を紹介することで示されている。
南ドイツのロットヴァイル市では、石油よりもクリーンな天然ガスを使ったコジェネレーション(熱電併給)システムをブロックごとに導入している。ピーク時の電力使用を減らすのが目的である。電力会社は、ピーク時の電力需要を満たすよう設備投資をするので、どうしても過剰になり、コストを上げると共に環境を汚染する。市のエネルギー供給事業所所長のレティッヒ氏は、工場や公共施設の協力をとりつけ、電力需要のピークをカットするのに成功した。日本でもビル単位でコジェネ導入はあるが、ブロックでは少ない。
北ドイツのブレーメン市の建築家グロッツ氏は、車のない住宅地を提案して市に採用され、市の都市計画課の一員となって、自らその建設を進めている。市民が共同で車を使用するカーシェアリングの普及や、路面電車、自転車道路網の整備なども並行させ、利便性は確保している。
ドイツが環境先進国である一つの要因は、環境団体の活動が活発なことである。たくさんの会員を擁し、潤沢な資金を使ってロビー活動もするので、政治家も彼らの意向を無視することはできない。また、生徒へのごみ教育を進め、ついにごみのない学校を実現した小学校長、天然材料を使った塗料のビジネスで成功した若者など、小さなことから大きなことまで環境保護のアイデアがあふれている。
(T)
(白水社、本体1800円)
著者はカナダの文化人類学者。ブリティッシュコロンビアの新興ビジネス階級の調査やアイルランドの漁村、ニューファンドランドの青少年非行と、家庭などのフィールドワークを経て大量殺人の研究に取り組むようになった。1989年に発表した『大量殺人者の誕生』は全米でベストセラーになっている。
冒頭に紹介されているのは、1988年に東京で、14歳の少年が両親と祖母を包丁で刺し殺した事件。それぞれ数十回も刺すという凄惨な殺し方の後なのに、髪を洗って好きな歌手、南野陽子のビデオを見ていたという少年の不思議な行動が大きく報道された。しかし、著者によると、家族殺人をした子供たちは、犯行後はぞっとするほど冷静で、後悔の様子を見せないという。そして、自分が間違ったことをしたとは全く思っていない。犯行は異常だが精神異常ではない。
本書では9件の事件をとり上げ、子供たちが殺意を抱くまでになった過程の解明を試みている。著者が注目したのはその家庭環境である。家族殺人は、とくに上昇傾向の強い中流階級で起こっている。両親が自らの社会的欲求実現のために子供たちに依存し、それが子供の大きな負担になっているからだ。子供は両親の支配から逃げようとするが、追い詰められ極限に達すると、殺人行為となって爆発する。「子供は自分をとりもどすために、家族を抹殺するしかないと考える」という。東京の事件もまさしくそれに当てはまる。勤勉で教育熱心で裕福な上級中流家庭であった。
それぞれの事件において、子供たちが追い込まれていった過程が描かれているが、そのパズルの一つでも外れていれば、殺人には至らなかっただろう。同じような問題を抱える家庭は少なくない。事件は特殊な例外ではなく、現代社会の問題が凝縮されたものであることが分かる。
(T)
(草思社、本体1900円)